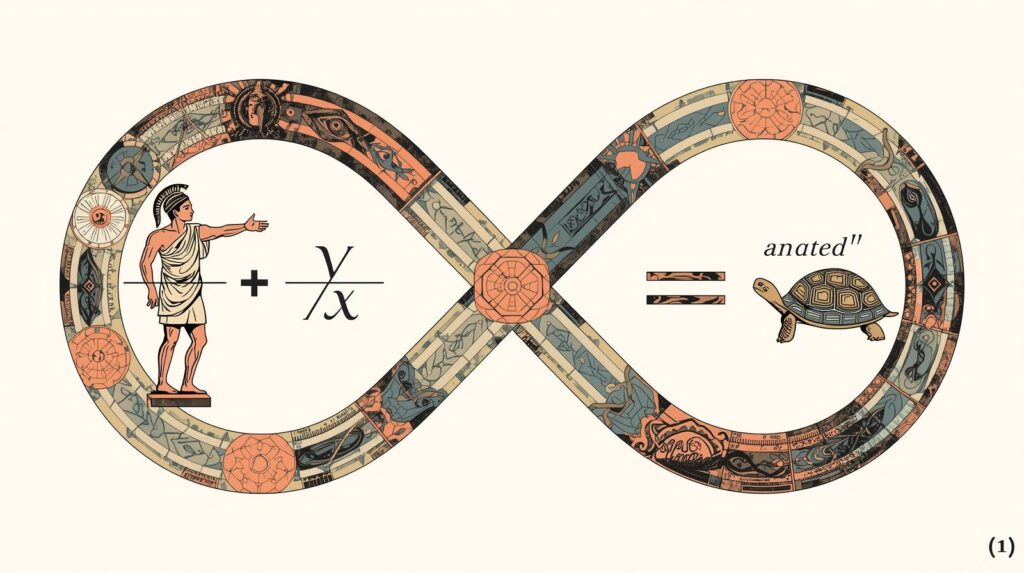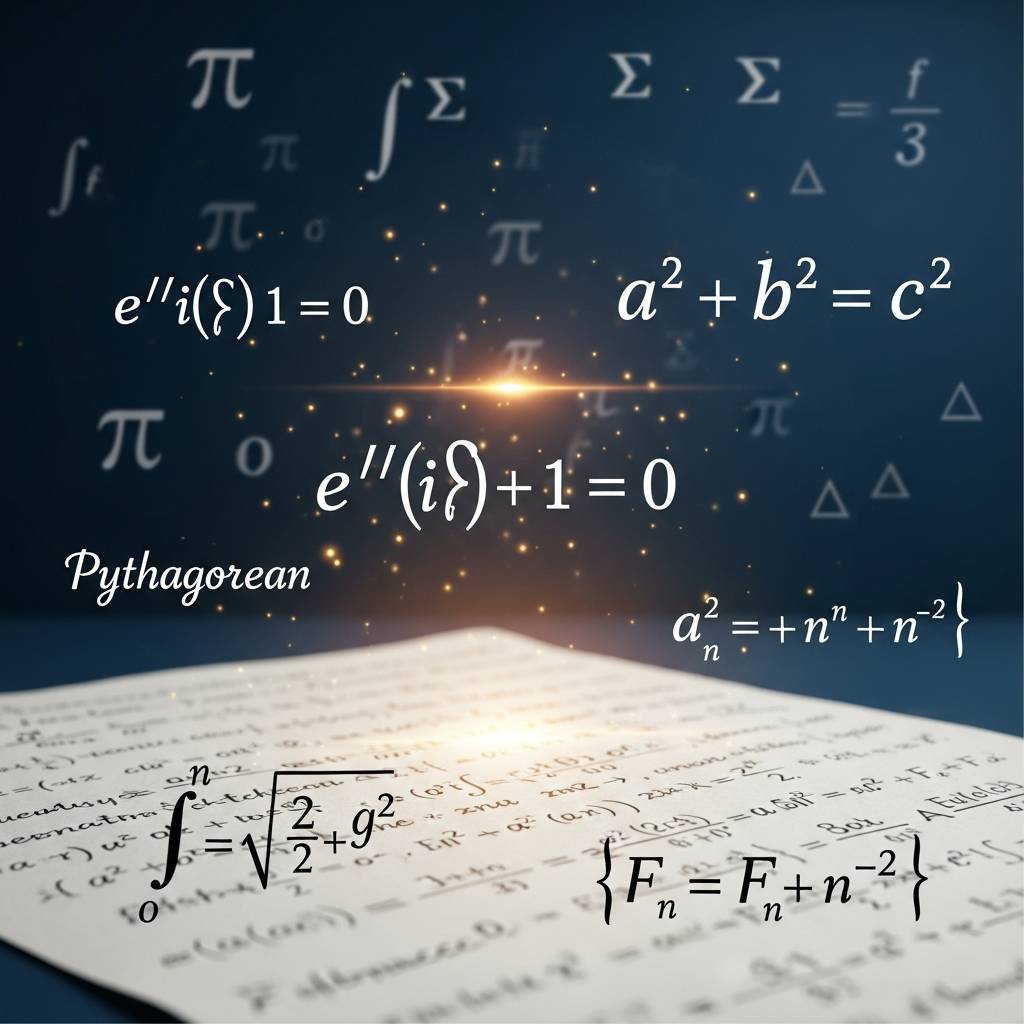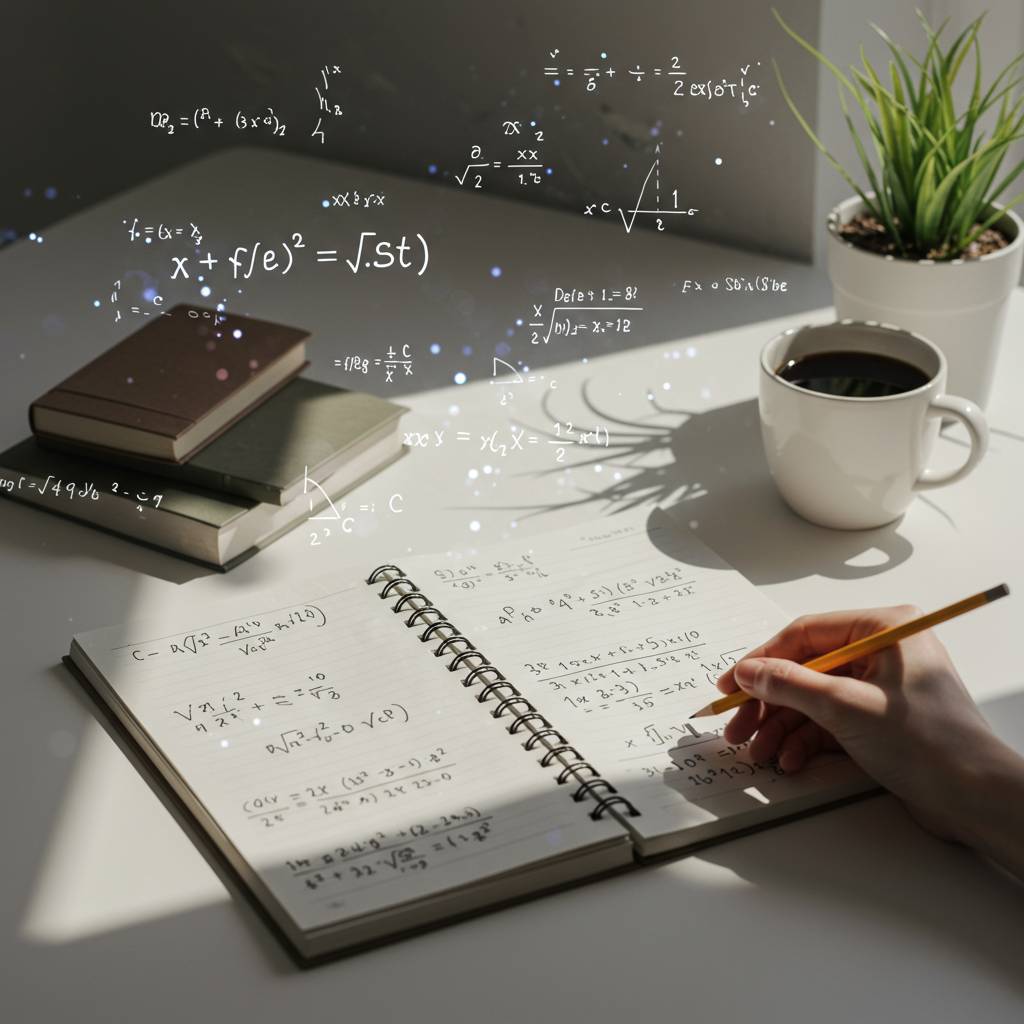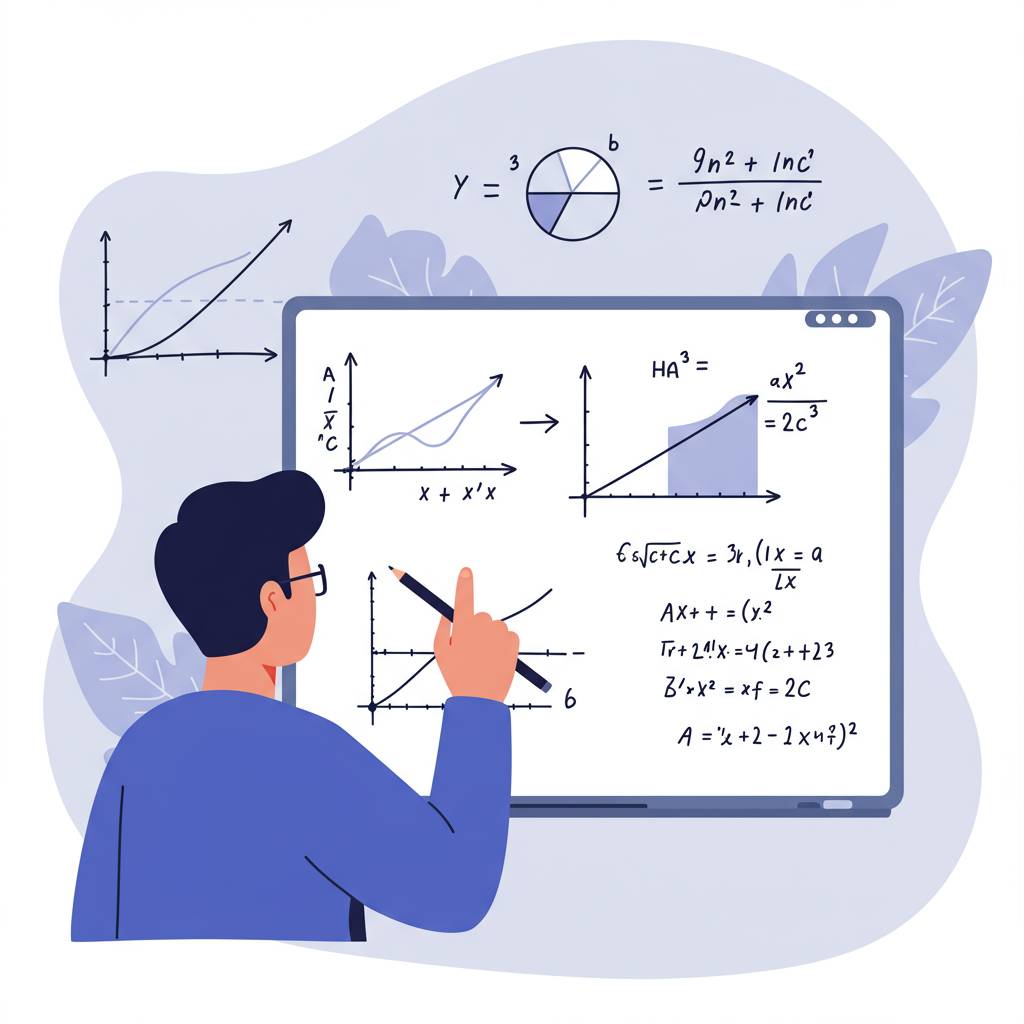数学– category –
-

無限級数とは何か:アキレスと亀が教える“1/n の壁”と収束の本質
導入:アキレスと亀が示す “直感と論理のズレ” 「アキレスは亀に追いつけない」──この逆説を最初に聞いたとき、多くの人は不思議な感覚にとらわれます。アキレスは速い。亀は遅い。それなのに「無限に追跡を細かくしていくと、いつまでも追いつかないよう... -

数学の美しい定理トップ10 – 専門家が選ぶ感動の数式
数学を愛する皆様、そして数学の美しさにこれから触れたいと思っている皆様へ。数学は単なる計算や公式の暗記ではなく、その本質は調和と美にあふれています。今回は「数学の美しい定理トップ10 - 専門家が選ぶ感動の数式」として、数学界で最も美しいとさ... -

数学的センスを磨く日常習慣 – 論理的思考力が自然と身につく方法
論理的思考力や数学的センスは、特別な才能ではなく日々の習慣から培われるものです。「数学が苦手」とお悩みの方も、実は日常生活の中で無理なく数学的思考を鍛えることができるのをご存知でしょうか?本記事では、AIと数学の専門家の視点から、誰でも実... -

数学が苦手でも理解できる!5分でわかる微分積分の基礎知識
「数学が苦手」という言葉に共感して思わずクリックしてしまった方、こんにちは。微分積分という言葉を聞いただけで頭が痛くなる経験はありませんか?高校数学の中でも特に難しいとされる微分積分ですが、実はその本質は私たちの日常生活にも深く関わって... -

サイコロとは何か:100%が存在しない世界で「偶然」を設計する
サイコロという装置:小さな立方体に宿る「ランダム生成」 サイコロは、手の中で完結する最も身近な乱数生成装置だ。6つの面に1〜6の目が刻まれ、理想的には各面が同じ確率で出る。だが現実のサイコロは素材・重心・角の丸み・表面摩擦・投げ方などの要... -

無限と無
人工知能(AI)技術が日々進化する現代社会において、「無限と無」という哲学的概念とAIの関係性について考えたことはありますか?AIが持つ可能性の無限性と、人間の思考では到達できない領域、そして計算の基盤となる「0(無)」の概念は、実は深く結びつ... -

数とは何か:世界を比較する感覚としての「変化の最小単位」
数とは何か:感覚が生み出す世界の比較 数は、世界を比較するための装置である。 人は何かを感じるとき、そこに必ず「違い」が存在する。 その違いこそが、数の始まりだ。 光が強くなった、風が弱まった、音が遠くなった—— それらの感覚はすべて、変化を検... -

現代物理学における無限と無の謎に挑む科学者たち
現代物理学における無限と無の謎に挑む科学者たちの物語は、人類の知的好奇心を刺激し続けています。宇宙の始まりから終わりまで、そして存在と非存在の境界線に至るまで、科学者たちは常に未知への挑戦を続けてきました。本記事では、量子論と相対性理論... -

螺旋とは何か:自然・数学・生命が選び続けた「回転しながら前進する形」
螺旋とは何か:循環しながら前進する「生成の軌跡」 螺旋という形には、直線や円にはない「時間性」が宿っている。円は同じ場所を回り続け、直線は遠くへ進んでいく。だが螺旋は、回りながら進む。循環と前進の統合された軌跡であり、海の貝殻、台風、銀河... -

黄金比とは何か:1.618が生む美と調和の秘密──数学・自然・デザインが惹かれる理由
黄金比とは何か:人はなぜ「1.618」に美を感じるのか 自然、芸術、建築、デザイン──分野をまたいで繰り返し現れる「黄金比」。その値は約 1.618。古代から現代に至るまで、人はこの比率にどこか調和と美しさを感じてきた。なぜこの数は特別視され、神秘性...