目次
はじめに:内積に含まれる「見えない角度」
私たちは日常的に「方向」や「力の向き」といった概念を直感的に扱っています。しかし、それらを数学的に正確に表すにはどうすればよいでしょうか。その鍵を握るのが「内積(dot product)」です。
内積は、一見すると単なる計算式に過ぎません。けれども、その背後には「角度」「長さ」「影」「類似性」といった多層的な意味が隠れています。
ベクトル同士の関係を数値として捉えるこの仕組みは、物理学やAI、統計、3Dグラフィックスに至るまで、あらゆる分野の基礎を支えています。
基礎解説:ベクトルと内積の定義
ベクトルの向きと長さ
ベクトルとは「大きさ」と「向き」を持つ量です。たとえば、\( (x, y) \) という2次元ベクトルは、平面上の一点を指し示す矢印と考えられます。
ベクトル \( \mathbf{a} = (a_1, a_2) \)、\( \mathbf{b} = (b_1, b_2) \) の「内積」は次のように定義されます。
$$ \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 $$
これが「計算式としての定義」です。しかし、もうひとつの幾何学的な定義があります。
角度を通して見る内積
$$ \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta $$
ここで、\( |\mathbf{a}| \) と \( |\mathbf{b}| \) はそれぞれのベクトルの長さ(ノルム)、\( \theta \) は両ベクトルのなす角です。
つまり、内積は「片方のベクトルをもう片方の方向に投影したときの長さ × もう片方の長さ」として理解できます。
ベクトルが垂直のとき(\( \theta = 90^\circ \))には内積はゼロになります。これは「方向がまったく関係しない」ことを意味します。

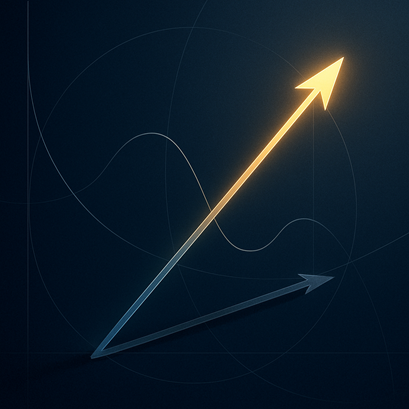
コメント